ここ数年、ファッション界隈のストリートブームやコーヒーのサードウェーブに引っ張られるように、オーナーがこだわりを持って運営をするインディペンデントショップが注目を浴びている。そうしたショップは、大手のチェーンやフランチャイズのように大規模な広告やプロモーションはできないが、Instagramなどの投稿や口コミによって人気に火がついている。インディペンデントショップの流行には、今のSNS時代も背景の一つにあるだろう。
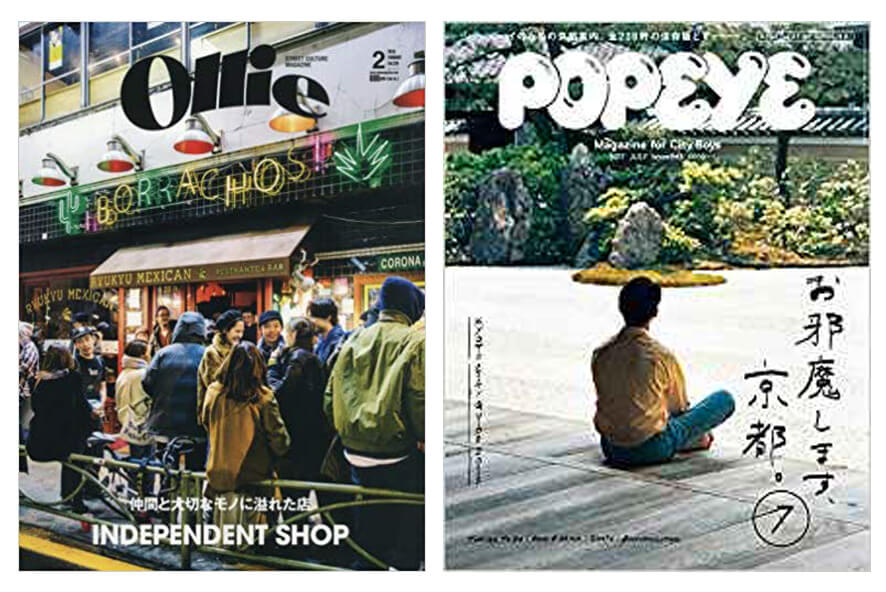
左:Ollie(オーリー) 2018年 02 月号 (INDEPENDENT SHOP 仲間と大切なモノに溢れた店) 、右:POPEYE(ポパイ) 2017年 7月号 [お邪魔します、京都。]
名古屋・大阪・福岡といった都市それぞれのオーナー独自のカルチャーを反映した個性派インディペンデントショップが注目される中、日本の古都・京都が盛り上がっている。
シティーボーイのファッション誌として創刊40年以上のPOPEYE(マガジンハウス社)が、2012年にリニューアル以降初めての京都特集を2017年に刊行するなど、”寺社仏閣だけではない、オシャレな街・京都”のイメージも定着してきた。
それを説明するのに欠かせないお店が、京都の繁華街・河原町にある。それが、サワー専門店・Sourだ。2016年にオープンして以来、感度の高い若者が京都に遊びに行くと合言葉のように「Sourって知ってる?」という言葉が飛び交う。
香港・東京・大阪と国内外でポップアップショップを展開し、最近では新宿・BOOK&BED TOKYOや、渋谷・KOE HOTELや、大阪・BIO TOPなどで期間限定コラボショップを展開し、注目が集まる。
インディペンデントとは”自由な・独立した”といった意味だが、その意味の通り何にも属さず、その上でこのように名を広め、注目されるコンテンツを生み出すために、一体Sourはどうやってきたのだろうか?

Sourは名前の通り、サワーの専門店。特徴は生のフレッシュフルーツをふんだんに使ったフォトジェニックなサワーを提供する。
オーナーの鈴木弘二氏は京都でカフェ経営をしたのち、2014年に”自分で焼く鳥”スタイル『炭火焼く鳥ソリレス』を京都河原町にオープン。その後、 2015年に東京・渋谷で炭火焼肉店『shibuya8929』をプロデュース、その後2016年にスタンディング酎ハイ専門店『Sour』をオープンし、2017年には京都・祇園の複合施設に『サワーガーデン』をオープンさせた経歴を持ち、京都・東京で飲食店を立て続けに成功させている。
鈴木「20歳頃まで大阪でバーテンダーをしてたんですよ。そこのマスターと一緒にやろうってことになって、京都でカフェ経営をそこから5〜6店舗展開しました。
Sourを思いついたのも、20歳くらいで。普通の居酒屋のチューハイって、フルーツのシロップなんですよね。レモンとかグレープフルーツは絞って使うのに他の果物はなくて。だったらいろんなフルーツを生で入れて、サワーとして出したら絶対流行るんじゃないか、って思い立ちました。まずは独立してから始めた1店舗目・炭火焼く鳥ソリレスでサワーを出してたんですけど、サワーが人気になったのでそこからサワー専門店を出したのが経緯ですね」

フルーツが鮮やかでインスタ映えするサワーとしても話題になっているが、SNSを中心にプロモーションを仕掛けているのだろうか?
鈴木「Sourは、インスタ映えと言われることもよくありますが、最初から意識していたわけではなく。これ絶対いけるし、面白い!と思っていたのでそれを発信したかったのが最初ですね。そしたら気づいたらフォローやいいねが増えていて。今は、Instagram経由で来てくれるお客さんは多いです。とはいえ、最初からソーシャルは意識していましたね。焼く鳥屋・ソリレスをオープンする際、施工前から紙にFacebookとInstagramのハッシュタグを書いて貼っておいたり。焼く鳥屋・ソリレスのロゴマークは、手遊びの鳥の形なのですがお客さんがInstagramでソリレスの写真を載せるとき、同じポーズをしてくれます。ポーズが一人歩きしてくれて、全く関係のない場所でもやってくれてハッシュタグで#ソリレスって投稿してくれたりも。あと、エゴサーチはめっちゃしてます(笑)Sourの投稿には全部、いいねをつけてますね」

焼く鳥屋・ソリレスのロゴマークのネオンサイン
参考にしたブランディングもなく自分の感覚、と鈴木氏は答える。
鈴木「SourのSNSアカウントはInstagramだけ。これはこだわってやってますね。
掲示するポスターのイメージビジュアル用に、イメージモデルやヘアメイク、カメラマンを雇っています。Sourのためのクリエイティブチームが出来上がっていますね。
あと、アパレル業界とは相性が良くて、コラボしてビジュアルを作ったりしています。うちのモデルを使って、ブランドの服を着てという感じで。
飲食業界のコミュニティーだけで狭めずに、業界を横断していいものを作りたいといつも思っていますね。特にInstagramではビジュアルが大事なので、商品の写真だけの投稿ではなく、モデルを使ってシーンの訴求をしたり。
Instagramは日々の投稿に担当のスタッフがいるんですけど、毎日どんな写真を投稿するか確認を毎回していて。ちょっと違うな……ていう写真には、「なんでこれがいいと思ったのか」って聞いています。ダメだしすることもあるんすけど、正解不正解はないからそこのジャッジは自分の感性だけですね(笑)」
イメージモデルを使ったSourのクリエイティブ
アパレルブランド・アダムエロペとSourのコラボビジュアル
鈴木「あと店舗としてSourを構える前に、何度かポップアップショップとしてSourをやっていて。そのときにまず、ロゴや販売用のTシャツを作りました。あとSNSも。
店舗より先にTシャツを売ってる飲食店なんてないじゃないですか?それおもしれー!てなって作って売りましたね(笑)
そのときに来てくれたお客さんは、いまもSourに来てくれています」
飲食店の運営に、モデルやカメラマンといったクリエイティブチームがいるのは珍しい例だ。
正直、Sourが有名になり始めて以来、似たようなサワーを出す店は増えていると聞く。
実際、東京にもフルーツサワー専門店を謳うお店が何店舗かある。
それでも京都のSourだけがブランド力を持ち、様々な業種とコラボできているのはクリエイティブにも反映されているセンスの良さが際立っているからだろう。
そもそも、京都でやり続けるとはどういった意味があるのだろうか?
鈴木「京都は大学生の街でもあるし、芸大や美大の数も多い。感度が高い若者が多いんですね。
最近京都のストリートカルチャーも盛り上がってきてますが、東京ほどビジネス感もなくいい意味でゆるさがある。その感じも、なんていうか今っぽいですよね。ゆるく繋がっていいもの作ろうぜ、ていう空気感。そいでもって、京都は一つのブランドでもある。僕は大阪の人間ですけど、京都で勝負しようって思ったのは「京都から来ました」ってそれだけでいいもの感あるじゃないですか。東京の人は京都好きも多いし。
Sourを始めた頃から、「東京でやったら絶対流行るよ」ってめっちゃ言われるから早々に進出しようと思ってたんですよ。でも、一方では「東京でやったら駄目だ」とも言われて。京都にあることがブランディングになることに気づいて東京は期間限定でポップアップショップとしてコラボで出店しています。ポップアップだと『京都のSourが東京に来た!』って喜んでくれるんですよね」
京都に比べ、東京はとにかくスピードが早い。ブームになって当てることができる場所だが、その分消費されてすぐに終わってしまう可能性もある。
そういう意味で、Sourは拠点が京都にあり、地元にきちんと根付いている。そのブランド力を活かしながら東京は期間限定での出店、という選択をとったからこそ定着した人気とブランドがあるのだろう。
鈴木「昔、ジンギスカン屋をやってたんですよ。中目黒でジンギスカン屋がヒットしたのを見て、関西にないなと思って始めたんですけど失敗しました。そのときは「流行ってるからいけるっしょ」って気持ちではじめたんですけど、「こんなん好きでしょ?お洒落でしょ?」て感じでお店を始めても大抵うまくいかないって思いましたね。自分が好きなことではじめることが大切で、正しい」
SNSが当たり前になり、誰かの価値観や趣味嗜好が可視化されている現代社会で、インディペンデントショップが流行る理由はそこにある。誰かがいいと思っているものではなく、「その人がいいと思っているもの」に価値があるのだ。インディペンデントショップにはまさに、オーナー独自の視点で「良い」と思う感性が詰まっている。バズることが注目され、流行り廃りのサイクルが加速する中、一方でそれらに流されない”その人なりの正しさや価値観”を求める時代でもあるのだ。
鈴木「コラボや、ポップアップショップをしたいという声はよくかけてもらいます。が、うちである理由がないとことはやりたくないし、やらないですね。例えばフェスとかクラブでの出店とか、絶対に売れるのはわかるけれど別にSourじゃなくても良いようなコンテンツだったらやらないです。最近だと新宿にあるBOOK AND BED TOKYOや渋谷のKOE HOTELでポップアップショップをしてますが、観光業やアパレルといった異業種かつ広がりがありそうなところとやらせてもらってますね。あと、美容室でお客さんに提供して、店の前で販売させてもらったり。やるからにはお互いに意味があることか、面白いと思えることじゃないと、やらないと決めてます。僕は好きと嫌いがハッキリしてるので、嫌いなことはやらない。それは経営でも同じです」
ヒビヤ セントラル マーケットでのポップアップショップ
東京や香港でのポップアップショップは旅費や経費で黒字にならないことの方が多い。が、それでも後々「あのお店と組んでやっていたんだ」というのがブランディングとして効いてくるから展開をしていると、鈴木氏は言う。
とはいえ、そういったコラボやポップアップショップはそう簡単に実現できるものではない。どうしてSourはオープン2年にも関わらず幅広い展開ができているのだろうか。
鈴木「自分から営業みたいなことをしたことはないですね。SNSのDMでよく声をかけていただくのですが、そこから実現したこともまだないです。いままでのコラボも、人の繋がりで実現してます。知り合いの知り合いが興味を持ってくれていて、だったり。
面白いと思ったものにはすぐ食いつくので、スピードは早いですよ」
目先のビジネスのための展開に走るのではなく、ブランディングになるようなコラボを選ぶ。
そこには自分の持つコンテンツが、”どういうもので、他者からどう見えているか”を見極める力が必要だ。そのうえで、守りに入りすぎるのではなくこれだ!と思う時には素早く行動をする。
それがSourがいまのイメージを守りながら次々とポップアップショップを実現させている理由だろう。
そんな鈴木氏が見る、今後のビジョンとはなんだろうか?
鈴木「脱Sourですね(笑)3年経ってブランドが確立されてきつつあり、Sourの鈴木さんって言われるのが若干恥ずかしい(笑)
Sourは僕にとってはファッションでいえばドメスティックブランドにしていきたくて。
流行のサイクルの早いファストファッションではなくて、飽きられるのは分かっているけれど、素材がよければ長く着てもらえるものにしていきたい。どこかや誰かの真似はしたくないし、カッコイイことをしていきたいですね」
ミーハーで好きなものが多いと語っていた鈴木氏。自分なりの信念はブラさず、興味関心にアンテナを張り続け、好奇心がつきない人だからこそ、トレンドを俊敏に自分なりのセンスに反映できるのではないだろうか。そしてそれは、流行のサイクルが早い現代において必要な能力でもある。これからのSourや鈴木氏の手腕が、どのように展開していくか大変楽しみだ。
※COMPASSでは、独特の視点から事業を興したミレニアル世代へのインタビュー記事を掲載している。


