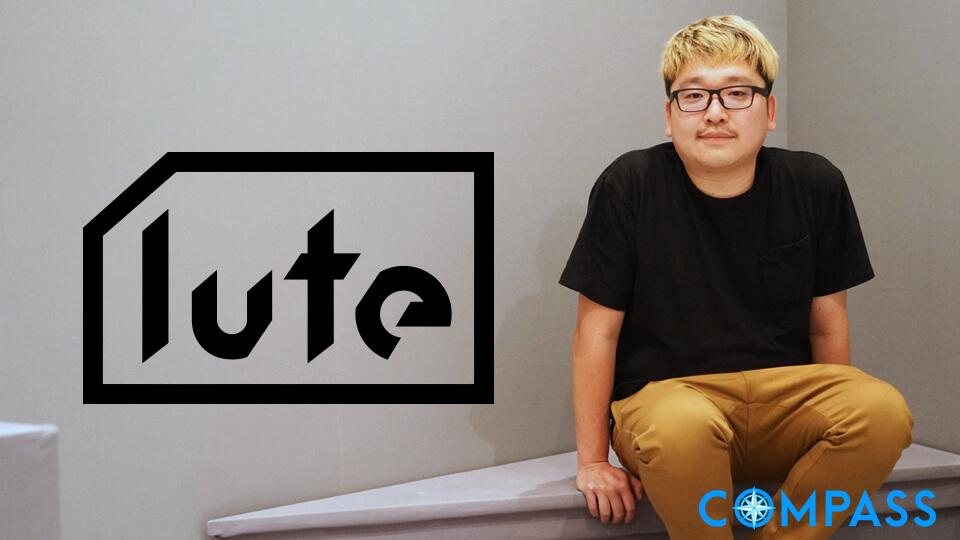2016年に動画分散型メディアとして発足し、様々な次世代を担うアーティストのミュージックビデオやライブ映像をYoutubeを中心に配信し、2017年8月より国内初のInstagram Storiesメディア「lute/ルーテ」をローンチしたlute。それから約1年のビジネスは、なにを目的とし、どのような結果となったのだろうか?今回代表の五十嵐弘彦氏に聞いた。

lute代表の五十嵐弘彦氏(編集部撮影)
――Instagram Storiesのビジネスを日本で大々的にやり始めたのはluteが最初だと思います。手応えはありましたか?
Instagram Stories(以下ストーリーズ)のビジネスをはじめた目的はグロースハックを重ねてPV数の稼げる投稿をしよう、といったことではなく、熱量の高いコミュニティを醸成することが目的でした。ストーリーズの事業をはじめて1年ほど経ちますが、結果は良かったですね。luteは分散型の動画メディアという考え方からスタートしました。
luteのロゴが入っているライブ映像やミュージックビデオを制作し、Youtubeなどのプラットフォーム上で発信することをまず始めました。それはもちろんluteというブランド認知もですし、カルチャーや世界観を作っていきたいと思っているからです。WEB上でもリアルな場所でも、人が集まるところには熱狂が生まれて、そこにはカルチャーが生まれて仲間意識が生まれていきます。
つまりは、「あの集団・あの界隈」という特定の趣味嗜好や空気感をまとった集団が醸成されていくんだと思っています。それを作ることこそがメディアを通してできることだと思いますし、ストーリーズはそのための手段でした。

ガールズバンド・CHAIのメンバーのユナ主演のInstagram Storiesオリジナルドラマ(左) HIP HOPユニットchelmicoがレポーターとして出演する「GRAND KIRIN」と「FNMNL」のコラボ企画番組(右)(lute提供)
――luteを通してカルチャーを醸成していくということですね。ストーリーズを通してまさにカルチャーがどんどん醸成されていっているということですか?
そうですね。「アカウントに何フォロワーいるから広告費いくらで……」というメニューだと思われがちなのですが、実際は全然違います。luteの周辺にいるアーティストやクリエイターを使って「あの界隈」の人たちにリーチしたいから、luteに発注してくれる、ということが多いです。その窓口としてストーリーズで自社の色を発信できることが一役買っています。まず最初にあるのがカルチャーを醸成するための世界観の発信で、そしてそれに紐付くクライアントができる、というのが今のストーリーズビジネスの内訳ですね。
――それは他社がストーリーズでビジネスをしようとしてもなかなか真似できないことかと思います。そういった界隈やカルチャーを醸成するために必要な要素ってなんでしょうか?
シンプルに編集力ですね。そのカルチャーがどれだけ好きか、その界隈を守るっていう意志と編集力。編集力というのも、Webメディアの編集力って意味ではなく、自社のブランドやロゴがどういう風に人に見られているかというのを考えられる能力だと思います。
――なにかと定量的に測りたがる昨今ですが、そういったカルチャーに紐づく空気感や熱狂というものは数値化できるものではないですよね。
そうですね。ですが、一定の趣味嗜好を持っている人たちの集団、というのがこれまでのレコード会社やレーベルといった音楽ビジネスの在り方だったんですよね。あそこのレコード会社の、あのレーベルの特徴はこういう系で、こういう人が所属してるよね、といった感覚的なもの。
そのことを、「界隈」って呼んでるんですけど、「あの界隈」って言われる空気感をどうやって作っていくかという、定量的には測れない、定性的な付加価値自体が音楽ビジネスに大切なものなんです。
カルチャーや界隈が自社で確立されていくと、クライアントにも理解してもらえるし、出演するアーティストも同調して継続して出演してくれる。この2つが掛け合わされるとどんどんビジネスを産める状態になっていきますね。そういった付加価値のある世界観を音楽を通して作っていくのがluteのミッションです。

Instagram Storiesで展開されるドラマ『それでも告白するみどりちゃん』(lute提供)
――そういった世界観を作ると思い至った経験はなんだったのですか?
音楽・エンタメ業界は、メディア・レーベル・出演者(アーティスト)の3つの構造で成り立っています。ムーブメントを起こすためには、主要なテレビ局・大手広告代理店・メジャーな音楽レーベルが組んでマーケティングを行うのが当たり前な世界でした。アメリカは日本より何歩も進んだ音楽ビジネスなのですが、アメリカだとそれがどういう風になってるかというと、かなり面白いんですよ。
まず、スモールセグメントを相手にしたグローバルなミレニアムメディアが大量にある。例えば、VICEやHYPEBEASTとかがそうですね。そのメディアを通して音楽業界にどういうことが起きてるかって言うと、例えばラッパーが買ったばっかの車を電柱にぶつけたとInstagramに投稿するわけです。
そして、それを一番最初に記事にするのはミレニアルメディアで、それを見て中堅どころのテレビ局が拾って、それを最終的に大手のニュース局であるCNBCとかが拾って大事になる、というような流れ。そうなると、なぜかSpotifyの再生回数が増えたり、CMが来たり……みたいなことが起きています。
かつ、面白いのは企業側もその価値を分かっているから、ナショナルクライアントがミレニアルメディアのコンテンツに対して広告主になるという流れもあって。そういったスモールセグメントの中のスモールヒットっていうものがいくつか出ている流れがあり、それがグローバルに繋がっていくという流れがアメリカでは起きています。
この流れはますます主流になるはずだし、日本でもそうしていきたいって考えたら、自分たちでメディアもレーベルもアーティストも全部持ってることが絶対条件なんです。日本ではミレニアルメディアの元気さと影響力もアメリカと比べるとだいぶ劣るので、まずはメディアとしてある程度元気なものにならなきゃいけないってところで、ストーリーズも含めた動画メディアをやっています。
――アメリカは、マーケティングだけでなく、音楽のビジネス自体も日本と比べてどう違うのでしょうか?
音楽のサブスクリプションサービスが国内で伝播した今、音楽はデジタル化したその先の世界、つまりはポスト・デジタルの世界になっています。そこでどうやったらミュージシャンが稼げるかと考えると、アメリカの音楽ビジネスは数倍先に行ってるんですよ。アーティストがめちゃくちゃ稼げてて、ラッパーがプライベートジェットに乗っていることとかがザラにあって。
CDなどの音源自体の売上げは下がっている中で彼らがなにで儲かっているかというと、理由は2つあります。1つ目は、ライブなどの興行が確実に儲かっている。ライブで稼げるシステムが出来上がっている。
2つ目は、アーティスト自身のブランド化が始まっている。例えば、アディダスやアンダーアーマーなどのアパレルブランドがリブランディングしたいという理由でアーティストに広告塔になってもらって商品開発をするということが起きているんです。
他にもオリジナルのアパレルブランドが大成功している例や、音楽から派生してヘッドフォンを制作し、それがAppleに買収されたといった事例もあります。
――アメリカはデジタルの普及によって変わってくという実感にいち早く気づき、音楽ビジネスのシステムを変えていったんですね。
2000年半ばにはCDを売るビジネスモデルがそろそろやばいんじゃ?と気付き始め、2000年代後半から新しい動きが花開き始めた印象です。そういった流れに乗った音楽ビジネスシステムの再構築に、日本は遅れている。
ここ12年間くらいの間に日本の音楽業界の中でも、「コピーのできないコントロールCD」とか「サブスクリプションサービスは無い」とか「音源をYouTubeにあげるな」とか色々あったんですが、そういう論争は一通り終わったと感じます。
確かにデジタルの普及によってCDが売れなくなるだろうし、伴って廃れていくビジネスはあるけれども、音楽自体は普遍的なもの。時代の流れに対して音楽に伴うビジネスのフォーマットは変わっていくけれど、それがなくなることはないんです。そういう意味でも日本の音楽業界のビジネスモデルを変えていく必要がありますね。
ー後編では、今年6月に韓国のHIPHOPレーベルとの業務提携を発表した五十嵐社長に、なぜいま韓国がアツイのか、紐解いてもらいます。